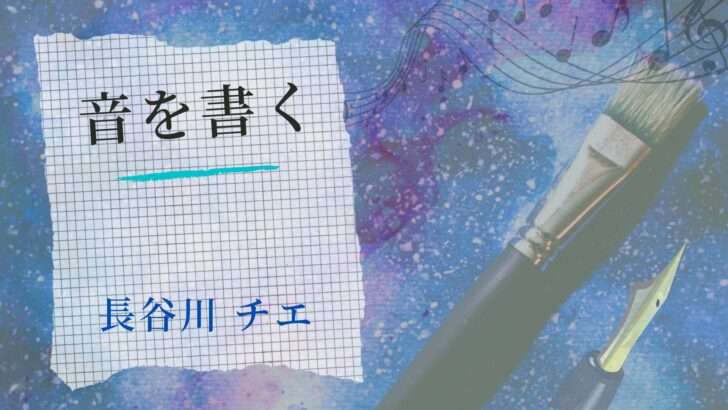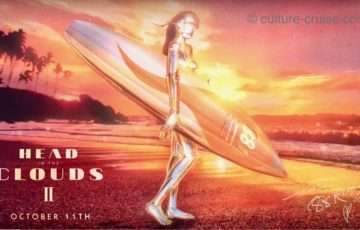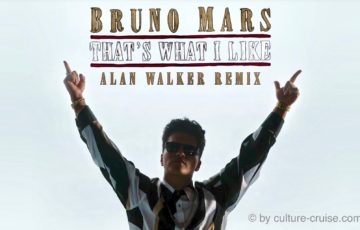連載小説「音を書く」序章〜第二章
序章 プロローグ
望(のぞむ)が指定した場所には、原稿が入った分厚い封筒がたしかに置かれていた。
病院の中は季節がないけれど、裏庭に一歩出れば、桜色のうららかな世界は今年も始まっていた。ベンチに腰をかけて、原稿を広げる。
「今から僕は、君に伝える音を書きます」
これがこの物語の最後の一文だった。
私は小説を読む時、最後の一文を先に読んでしまう癖がある。時間を巻き戻して、辿り直す。自由にタイムトラベルができるのは小説の醍醐味だ。最後の一文を読んだところで、物語の全貌までは意外と分からないものだ。
病室には音がない。それでも、諦めず私に音楽を届けてくれるのは望だった。
別に歌ったりするわけじゃないけれど、彼はいつも私に言葉で伝えてくれる。日記みたいな時もあれば、詩のように短い時もあって、彼の文章はテンポがよく、まるで音が宿っているような気がする。だから私は、その文章にインスピレーションを受けて描く。
私からすれば、望の文章は十分魅力的だけれど、本人にしてみれば上手く書けたと思えることはほとんどないという。
望にとって、私に届ける文章は「自分を見失わないための訓練のようなもの」だとも語っていた。彼の文章には色がなく、私の絵には音がなかった。
彼は書けず、私は描けない。私たちは支え合って生きている。
この日受け取った原稿は、望にしては珍しく長いようだった。短いメッセージの後に、物語は始まった。
「これは僕の長い独り言だから、感想はいらない。読んでくれるだけでいいんだ。今から三カ月前のある一日。音楽と僕と、描く人の物語。きみの音が導いてくれたストーリーだ。」
第一章 サンタクロース
この世のすべては、誰かの諦めなかった心でできている。
たとえばサンタクロース。
きみはサンタクロースっていると思う? そんなわけないじゃんって笑うかな。それとも優しいきみは、いるかもしれないねって、返事をしてくれるかな。
友達に「サンタクロースはいない」って聞かされたのはたしか15年くらい前。その瞬間、僕は意外にも落ち着いていて、妙に納得したのを覚えているよ。
それよりも、僕を喜ばせるために、母さんは毎年クリスマスの演出を考えてくれていたということの方が、母子家庭で育った僕にとってはよっぽどリアルで大切だった。もっと早く気付いてあげるべきだった、とさえ思ったほどだ。
世間からはひとり親の家庭で育った人を、どこか「受け取った愛情が半分」とか「かわいそうな境遇の人」という見方をされたりするけれど、そういう人だからこそ気付ける幸せとか、持てる優しさ、感じられる愛や痛みがあると僕は思っている。
よくよく考えてみると、「サンタクロースはいません」って正式発表されたわけでもないし、もしかしたらいるかもしれないって考えることがあるんだ。
80代になってもサンタさんが来るのを待ってるおじいちゃんがいたら、「どんなに幻想的な80年間を過ごして来たんだろう」って思わない?
80年もの間、サンタクロースの存在を信じて生きることって可能なのだろうか。純粋さというより、想いを貫く強さが必要なんじゃないかな。
クリスマスの時期には、きみの目に触れる景色は少し変わるのかな? 僕はまだ、毎年きみがどんなクリスマスを過ごしているのか見ていないけれど、少しでも華やかな世界にいてくれることを願うよ。きみはきみでいてくれるだけで美しいけれど、多くの人を惹きつける魅力があると思うから。
きみと出会う前まで、僕はけっこうやさぐれてたんだ。行事ごとの大半は遠くから眺めるだけでよくて、自分の人生に取り込もうとは思わなかった。
クリスマスは肝心の当日よりも、その前の煌びやかな街並みの方が好きだし、いざ当日を迎える頃には、年末に開催されるフェスかお雑煮のことを考えてる。
小さい頃、母さんがお雑煮を作る姿を横でよく見ていた。年末年始のただでさえ忙しい時期に、丁寧に出汁から取ってとても手間がかかっているのに、雑なんていう漢字が使われていて、時々笑いそうになる。
こんなことばかり考えて生きているから、この前執筆の仕事も一本切られた。もう、書くだけで食べていくのは厳しいかもしれない。
そんな渇き切った僕でも、音楽を聴いている時は心が満たされたし、嫌なことを忘れられた。
第二章 星川 奏
その頃から聴き始めた、星川 奏(ほしかわ そう)というデビューしたばかりのシンガーソングライター。ピアノが抜群に上手くて、声もいい。容姿端麗、天資英邁、当代無双。四字熟語の魔術師か。
僕にないものをすべて持っているような人。名前からして、歌うために生まれてきたようなスターだ。そんなにたくさんの才を抱えて、一体どこへ向かおうとしているのか。でも、僕はそんな奏さんの音楽が大好きだ。今もほとんど毎日聴いている。
「奏さん」と呼んでいるけれど、彼は僕よりも三歳年下だ。なのにすごくしっかりしているから、自分の精神が救いようもないほど未熟な気がしてくる。
奏さんの素晴らしい作品がこの世に誕生している間にも、雑煮のことを考えて笑っているんだから、同じ人間として存在させてもらっているだけで感謝せねばならない。僕も前世でもっと頑張っておくべきだった。世の中は本当に不公平だよなぁ。
でも、僻んだり、妬んだりする対象にはまったくならない。能力の違いがありすぎるから、というのももちろんあるけど、それ以上に彼自身の人間性には、人のマイナスな気持ちをプラスに変える不思議なオーラが宿っているような気がする。
こんなに毎日聴いていても、その核心に触れることができずにいるから、オーラという実態のないものでしか表現できずにいた。こういう時、芯を捉えた言葉で表現できれば、僕ももっと必要とされるライターになれるのだろうか。
天から二物以上のものを与えられてもなお、人々から愛されている真相。僕は研究家にでもなったつもりで、奏さんのオーラを何度もたぐり寄せようとした。
それにしたって、二物以上のものをそんなに抱えることができるのだろうか。僕だったら両手からこぼれ落ちてしまう。
妬みじゃないんだ。だけど、一つくらい分けてくれたって良いじゃないか。そう思ってしまうほど完璧に見える。
その日も奏さんの曲を聴いていた。勝手に流れていると言った方が適切かもしれない。出かける支度をしながら、デビュー曲の「嘘やろ」を聴いていた。結局、ここに戻ってくる。
一見ふざけたタイトルなのに、ブラックミュージックのフレイバーをしっかり身に纏っているとは何事だ。こっちのセリフやん。「嘘やろ」って。よく却下されずに僕の家の良質なスピーカーまでたどり着いたな。二年前に一念発起して買った高級なやつだよ。
今まで誰もが目もくれず通過してきたものを、後ろから丁寧に拾い上げていったような、「その手があったか」と気付かされるような曲だ。それがこんな風に形になるのだから、人気にならないわけがない。
感度の高いリスナーは絶対に放っておかないし、何よりプロほど彼の才能を認め、感服している。そのうち日本全国奏さんフィーバーが巻き起こるんじゃないかという予感さえしていた。
ここで速報です。サンタなんていないと聞かされて15年。僕の元に、今夜の奏さんライブのチケットが届きました。サンタっているの? 僕の質素なクリスマスもここまで。ついに記録が途絶えるようです。
当選が分かってから、モノクロだった僕の毎日に色が付いた。どうして? 甥っ子にも、姪っ子にも使えなかった魔法だよ。
音楽の力だけでこんなに気持ちって華やぐの? ときめきとは何か、僕は問いたかった。その答えを確かめに行きたい。
部屋中の空気が冷たく澄み切っていたからだろうか。この世で呼吸をしているのがまるで自分だけだと感じるほど、いつになく空虚に思えた。
でも、僕にはライブという希望がある。明日への扉!! その後のことなんて考えもしなかった。やり残したことは全部明日。皿は帰ってきたら洗います。
僕は先延ばし検定一級取得者だ。先延ばし検定はデッドラインの何分前まで後回しにできるかを計測するものだ。一級の合格率はわずか1パーセントという狭き門。
僕は締め切り20分前まで2000字の原稿を白紙の状態で貫き、見事合格した。もちろん締め切り時間内に提出することは必須。提出物の内容も審査の対象となる。
こんな妄想をしている間に皿五枚くらいは洗えるが、そこをあえて妄想に費やすのが一級取得者のなせる技。達人としての意地だ。
もし世界が滅亡してしまうとしても、ライブが終わるまでのあと四時間、いや三時間でいいから待ってください。そう思ったんだ。
▼つづきはこちらから
▼小説の参考にしたライブやアーティスト、back numberについて