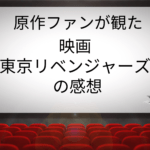Culture Cruiseで連載したWeb小説『音を書く』の執筆中に聴いた音楽をプレイリストにしました。モデルになったライブや、全体を通して聴いていたback numberについて、創作によって気付いたことも交えて書いています。
プレイリスト
今回のストーリーは音楽が主軸になっていたので、プレイリストを一つ作り、それをかけながら小説を書いていた。
作業にハマりそうな曲、頭に浮かんだ曲をプレイリストに入れていき、BGMとして流しながら執筆する。
違うと思った曲はリストから除外していく。これは好きとか優劣の問題ではなく、単に今回の小説とは方向性が違ったのだと思う。
歌詞の全体像は把握しているものの、歌詞に影響されて物語を書くことはなくて、意識はメロディと声の方にある。言葉は執筆に集中しているという感じ。意味分かんないですね。
ヴォーカルの声質も関係していて、例えば地声のロングトーンが特徴的な、はっきりとしたヴォーカルは不向きだった。それはそれだけ、気持ちを引き込む世界観を持っている声ということで、改めて魅力を知ることにもつながった。
曲順も、章の順番に沿って配置している。章に関係なくずっと聴いていた曲は、その間に散りばめてみた。メロウな曲が多いが、どん底に暗いわけでもなく、希望を灯すような曲が並んでいる気がする。
自分がそういう曲ばかりを選んで聴いているのだろうかとも考えたが、音楽とは音が鳴り始めた瞬間から終わるまで、希望に向かっていくものなのだと思った。
形は違っても、直接的でなくても、希望を分け与えてくれるのが音楽なのだと。自分もそんな文章が書けたらと思いながら執筆していた。
創作意欲を掻き立ててくれたアーティスト
書いているうちに、「この人の声だとなんか筆が進むなー」っていう感覚がだんだん分かってきた。
特に良かったのはyamaさん、DISH//の北村匠海さん、ヨルシカのsuisさんの歌声だった。繊細で美しいんだけど、ぽわぽわしてなくて芯がある優しさというか、なんとなく共通点がある気がする。
情景描写が上手いので創作を助けてくれるのかもしれない。芸術肌でもない私が文章で物語を創ろうとすると平坦になってしまうから、表現力の高い人の声を自然と欲していたようにも思う。
聴きながら書く時は、歌詞の意味を拾い上げるわけではないが、曲調が違うとフィットしない。聴いているようなそうでもないような、宙に浮いた感じが夜中まで何時間もループする。
この3人の声はその間も斜め後ろにいてくれるような、猫と人間みたいな一定の距離を保ってくれていた。一つの表現に縛られない自由さも良い。
表現の自由度で言えば、King Gnuの井口理さんのファルセットやミックスボイスも、型に嵌らないところが創作意欲を掻き立ててくれた。
このプレイリストには気付いたらKing Gnuの曲が4曲も入っていたが、井口さんのそんな魅力が感じられる曲を、自然と選んでいたような気がする。
小説のモデルになったライブ
序章から読んでくださった方は、この小説で意識されている特定のアーティストが思い浮かんだかもしれません。
創作活動において、「モデルはこれです!」と公言されることはほとんどないが、何かしらを思い描いている創作者は多い。プロセスを語れるのはある意味、無名ライターの強みなので、いろんなところでちょこちょこ語っている。
『音を書く』の原風景、この小説のライブシーンでイメージしていたのは、藤井風さんのライブだった。
▼以前「ネタバレのないライブレポート」として記事にしたライブです。
藤井風『HELP EVER HALL TOUR』ネタバレのないライブレポート
何となく「旅路」をイメージして書いたのは第六章。
第九章ではDISH//の「君の家しか知らない街で」に感銘を受けてオマージュのように作ったし、第十三章はTHE FIRST TAKEの北村匠海さんに助けていただいたと言いますか何と言いますか。
とはいえ、特定の誰かのことを物語にしているのではなくて、いろんな要素を取り込んで形成されている。ここでそのアーティストを挙げればキリがないほどだし、実際はほとんどの場面が、実在しない人に向けて書いている。
あくまでもリファレンスのつもりなので、イメージのヒントくらいの感覚で読んでいただけると嬉しいです。
back number
全編を通して、執筆しながら一番聴いていたのはback numberだった。
2004年に結成し、2011年にメジャーデビューしてから、数えきれないほどのタイアップ曲を書き下ろしてきた彼らは、最前線で映像に音楽を授けてきた。
これだけのタイアップをこなしながらも、ヴォーカル・清水依与吏さんの枯れない想像力と、ずっとシンプルにバンドマンで居続ける3人に尊さを感じて、これを機に聴き直したくなった。
「派手な演出などないのに、印象に残るのはなぜだろう」
余計なことなど語らなくても、曲の中でストーリーが生まれ、聴き手の数だけ感情を引き出し、完結されている。
それがこのバンドの魅力だと思った。それはまさに、私が記事や小説の中で実現したいことだ(なのにいつもごちゃごちゃ語ってしまう)。
今までの好きとは違った尊敬の念が湧いてくるようだった。制限のある中でストーリーを創造することの難しさを改めて感じた。
プレイリストには「ヒロイン」と「僕の名前を」を入れたのだが、それ以外に聴いていたのは「水平線」という曲だった。
コロナ禍で、インターハイが中止になってしまったことがきっかけで生まれた曲だという。下記は「水平線」MVの概要欄からの引用です。
新型コロナウイルス感染拡大は私たちの生活に大きな影響を与え、 back numberとしても心苦しい選択を強いられて来ました。 そんな中、インターハイが史上初めての中止という決定が下され、 それまで開催に向けて尽力してきた運営を担当する高校生たちからback numberに手紙が届きました。
学生時代に自身も陸上競技でインターハイを目指していた清水依与吏は、 今年のインターハイの開催県が地元・群馬県であったこと、 開会式で「SISTER」が演奏される予定だったことを知り、 何か彼らのために出来ないか考え、急遽制作し、完成した楽曲が『水平線』です。
執筆当時は発売されていなかったので、プレイリストに入れることはできない(のちにリリース)。だからYouTubeで時々この動画を流しながら書いていて、それが気持ちを切り替えさせてくれた。
今回のプレイリストは、小説の中の登場人物に向けて集めるイメージだったのだけれど、この曲だけは唯一、書き手の私自身が勇気をもらっていた。
この曲だけ居場所がYouTubeだったので、自発的に聴きに行くことで、心と頭の中を整理することができた。
広告も貼られていないし、高校生でもない自分がこの曲にできることは、再生回数を伸ばすことくらいしかなくてもどかしかったのだけれど、とても良い曲なのでぜひ再生ボタンを押してください。3つのシーンがワンカットで撮られているところも、感情が途切れなくて素晴らしいです。
待っている人がいるわけでもない作品を書き上げるのは、現在地もゴールも見失いそうになる。かっこ悪いけど、「もうやめようかな。今やめたって、どうせ誰も気付かないだろう」と投げ出してしまうことが何度もあった。
でも何とか執筆できそうな日を見つけては、この曲や、back numberのたくさんの音楽を聴いていた。この先の50年で1人くらいは、自分の作品に心を動かされる人がいるかもしれない。いなくても、自分が変わればいいじゃないか。そう気持ちを切り替えることができた。
いつもとは別の視点から人や曲の魅力に気付けたことは、自分にとって視野を広げる意味があったし、それが次の執筆に繋がっていくものと信じたい。
小説を書こうと決めたのは、アーティストの音楽活動を見て自分も何か創りたいと思ったからだけれど、最後まで音楽に助けられ、完成したのは『音を書く』という作品だった。
創作が創作を支え、それは単なる娯楽ではなく、人の心をも変えていくことが、この物語でどこかの誰かに伝わってくれていたら嬉しく思います。
文 / 長谷川 チエ

▼伏線を自分で解説してます