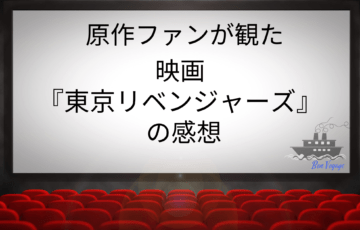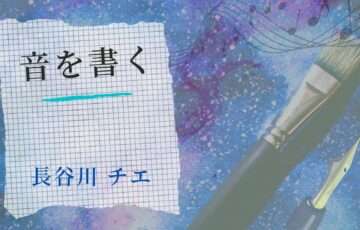『明け方の若者たち』について、小説と映画のレビューをそれぞれネタバレなしで書きました。
小説『明け方の若者たち』
本は旅に出る。旅に出るたびに、また本を買う。
小説『明け方の若者たち』を、私は2冊買うことになった。
1冊目
『明け方の若者たち』のハードカバーを吉祥寺の書店で見かけたのは、2020年の夏頃だった。
Webライターであるカツセマサヒコさんの初小説ということで、自分もライターの端くれとして、読んでおこうと思い購入した。
帰り道に井の頭線の電車内で本を開く。“明大前”の文字を見た直後に「次は明大前〜」とアナウンスが響き渡り、何だか嬉しくなったことを覚えている。
20代の“僕”の視点を通して、東京の景色とともに描かれる社会や人物、そして音楽。
その年代をとうに過ぎても、人生のマジックアワーは明日かもしれないなどと希望的観測をもとに生きてしまっているので、誰かのストーリーに触れて「自分にもこんな時代があった」と懐かしむことはあまりない。
だからこの物語と共有できたのは、下北沢や高円寺、明大前などのロケーションと音楽だった。
もっと細かい部分の感想としては、穴が開きそうな親友の靴下を見つめているシーンの描き方が印象的だった。単純な日々の重なりは複雑で、本当の意味でのリアルがハイコンテクストに詰め込まれている気がする。
数日で読み終わってから1ヶ月も経たないうちに、その本は下北沢に住む人の元へ旅に出た。誰かに貸した本やCDが戻ってくる確率はどれくらいだろうか。
本作の舞台として下北沢がよく出てくるので「下北沢にいる方が、本にとってはホームだろう」などと変なことを考えた。
2冊目
本の存在も忘れかけていた2021年11月、タワーレコード町田店で、タワレコ限定リリースのシティポップを試聴している時だった。ふと右手側に目をやると、「映画『明け方の若者たち』パネル展」が展開されていた。
「そうだ、映画がもうすぐ始まるんだった」
『明け方の若者たち』は映画の公開を目前に控え、小説は文庫化されていた。
存じ上げなかったのだけれど、POPによると町田はカツセさんゆかりの地だとのことで、映画の公開に合わせてこちらのお店でもバックアップされているようだった。

(※許可を得て撮影・掲載していますが全然上手く撮れていなくてすみません)
まるで他人の心の中を覗いているような感覚になる、カツセさんの細かな描写にまた触れたくなって、今度は文庫本を購入した。タワレコ町田店限定のしおりも付けてくれた(トップ画像のもの。裏もかわいい)。
文庫はサイズが小さい分、登場人物が手の中に収まるような気がして、何だかかわいく思えてくる。そして前回と大きく違うのは、演じる役者を想像しながら読むという楽しみ方ができる点だった。
彼女の存在を通して形成される僕。僕という存在を通して描かれる、沼のような5年間。
それでも、振り返れば全てが美しい
そう思えれば過去は変えられるのかもしれない。今日や明日をどう迎えるかにつながる、実はとても重要な捉え方かもしれない。そんな風に感じた小説だった。
映画『明け方の若者たち』
映画は2021年12月31日より公開された。
毎年元日には映画を観ると決めている。連れも道連れ。この日に観た作品はなぜかずっと記憶に残る。
2022年最初の映画はこの作品にすることにした。
結果、元日向けの映画ではなかった。もちろんそれは承知の上だったけれど。
昨年、実写映画の興行収入No.1作品で主演を務めたり、今年の朝ドラのヒロインに抜擢されたりする役者勢の最新作にしては、こじんまりしている。制作費もあまりかかっていなさそう。
きっと、話題性や名誉を基準に作品を選ぶ役者さんたちではないのだろう。そんな方々が第一線を走り続けていることが心強く思える。
でも人を惹きつける芝居をするので、結局は話題になる。そんな世界なのだろうか。
北村匠海さん演じる“僕”の中にはいつも、黒島結菜さん演じる“彼女”の気配がある。
ひと昔前ならそれは助演の仕事だったけれど、主張するだけが主演ではなくなった。
受けの芝居が上手くなければ成立しない世界になったし、それによって表現の世界は俄然面白くなったとも感じている。多様性の影響力は計り知れない。
黒島さんはご自身でも語っているように、「絶対に勝ち上がる」みたいな闘争心がないところが興味深い。にも関わらず、魅力が伝わってしまうところが好きだ。
もちろん頑張っていないはずは絶対にないのだが、貪欲さのなさが彼女のまなざしに余裕のようなものを湛えていて、今回の役にはそのメンタリティが合っていたように思う。
弾むような明るい声や天真爛漫な表情が、この作品の要になっている。
ベッドシーンについてはこういう場合、「体当たりの演技」などという決まり文句でまとめられるのだろうか。
しかし前に出すぎるわけでも、消極的すぎるわけでもなく、周りに合わせられる黒島さんのお芝居には、終始気持ちを預けることができた。
北村さんとの呼吸も合っていたのだと思う。公開前のインタビューで読んだ「そもそも恋愛においては当たり前のこと。僕自身には抵抗や大変さはなかった」という北村さんの力強い言葉が頭の中を駆け巡った。
井上祐貴さんはメインキャストの中で唯一、役名がフルネームで授けられている。それだけ小説の中でも人物像がはっきりしていたのだが、自分がイメージしていた尚人を、見事に再現してくれていた。
原作では“僕”を通して描かれる“彼女”や尚人の、呼吸する姿を観られることが映画版の楽しみ方でもあると思うので、それはとても大切な要素だと感じる。そしてこの作品をリアルなものにする橋渡し役にもなってくれている。
セリフではないト書きの部分を、映画でどのように描くかを悩んだと松本花奈監督がおっしゃっていたけれど、まさに浮遊していたイメージが、形になる瞬間を見届けられるのが楽しい。
気取りのない表情や、とりとめのない会話が「全部好き」という一言に吸い込まれていく。その引力は映画版ならではだったと思う。
また、個人的には佐津川愛美さんの出演シーンが、小説よりも一歩踏み込んで印象に残った。さまざまな感情がそこで交錯しているような気がする。
音楽
原作では、邦ロックが今にも聴こえてきそうな描かれ方をしている。
映画でももっと全面に出して良いのではないかとも思われたが、それは単に音楽好きな私の身勝手な願望かもしれず、また中途半端に音楽に頼る映画になることを、回避できているのかもしれない。
あるいは人によっては十分音楽が鳴っているだろう。そんな中でも主題歌を担当されたマカロニえんぴつは、この作品の盾になっていた。
エンドロールマニアの私は今回も、新鮮な気持ちでエンドロールを迎えるために、公開前からリリースされていた主題歌を封印して過ごしていた。
ただ自動再生にしていたSpotifyで流れてきた時、曲のイントロが映画のCMで聴いた印象と違ったので「本当にこの曲なのか?」という疑問を解決したくなって1度だけ聴いた。そしたらちゃんとこの曲だった。
マカロニの曲には「溶けない」「恋人ごっこ」などのように、ブリッジで急にカーブするみたいなギミック的要素が時々ある。
その日の帰り道、私のはしゃぎようは異常だった。1人でニヤニヤしながら、解禁された「ハッピーエンドへの期待は」を延々と聴いた(怖い)。
エンドロールを楽しむためにたった1曲を我慢してこんなに幸福感を得られるのなら、私のマジックアワーは今なのでは? とも思えるほど楽しい帰り道だった。
イントロのダブリングは大正解だったと思います。マカロニさんありがとう、大好きです。武道館公演行きます。
沼のような5年間
映画を観て特に印象に残ったのは、北村さんが作品の中で、5年間をしっかりと生きていたことだった。
撮影は約2週間ほどだったとも伺った(普通そんなスケジュールでは無理なので相当大変だったはず)。
小説では1冊をかけてたっぷりと描かれる歳月を、短い撮影期間の中で映像で再現するのは難しく、観客ですらも「はい3年後、了解。」みたいな妙に聞き分けの良い認識をしてしまう。
しかしこの物語のじわじわと経過する5年間は、ちゃんと北村さんの身体を通り抜けているように感じた。
実生活では、子役時代からの役者人生と並行してバンド活動を行い、役柄では高校時代にタイムリープしたり、自分の身体を亡くなった他人に30分間何度も占拠されたりしている。
一体どんな姿勢で時間軸を受け止めていらっしゃるのか、凡人には理解できない。時間を受け止めるブレない体幹のようなものが、北村匠海さんの芯にある。そんな気がしたのでますます興味は尽きなくなった。
過去の捉え方が、今日や明日の自分をつくっていく。小説でも映画でも、同じようにそう思った。
Amazon Prime Videoでは“彼女”のアナザーストーリーも配信されるとのことなので、そちらも楽しみにしておきたい。
あの本は今ごろどうしているだろうか。渡した相手は、恋人から友人に変わって、今はもう会えていない。
また別の誰かの元に渡って、旅が続いてくれていたら嬉しい。でも時々、もしかしたらあの本が突然帰って来るのではないか、などと考えてしまう夜もある。
人も本も旅に出る。旅に出るたびに、また本を買う。
文 / 長谷川 チエ
▼マカロニえんぴつについて
▼『東京リベンジャーズ』レビュー