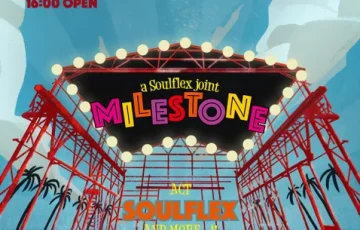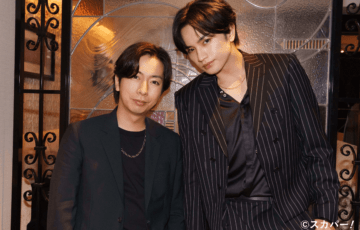まえがき
ーー私は記事を速く書くことができない。
締め切りはさすがに守るが、時間の許す限り深く考えては何度も書き直すので、いつも偉い人に怒られる。
この際、マイペースな自分だからこそ書ける記事を追求したい。少なくともここは自分のメディアなので、ゆっくり書いても怒られない。
下書きが溜まるのは、締め切りが無いせいだ。期限を設けないと、また今回も未公開のままかもしれない。
もうすぐ2019年が終わるので、いっそ来年末に完成としよう。2019年12月〜2020年12月までの1年越しの記事。これが良い挑戦、良い勉強になるように。
執筆のテーマは、藤井風さんの音楽について。この1年でどんな作品が生まれ、自分が何を感じたか、自由なレイアウトで綴ってみたい。
そして藤井風さんの音楽とはどういうものか、1年後の自分に教えてもらえることを楽しみにしています。
2019年12月
藤井風さんについて
2020年1月にデビュー。
1997年6月14日、4人兄弟の末っ子として、岡山県南西部にある人口1万人ほどの里庄町で生まれ育つ。
3歳頃から楽器を弾けない父にピアノやサックス、英語などを教わる。
小学校の終わり頃、「これからはYouTubeの時代だ」という父の一言がきっかけで、カバー動画などを多数アップするようになり、これがのちにデビューするきっかけとなった。
長期間の記事を書く理由はまえがきの通りだが、それ以外にも、
・ひとつのテーマをどこまで深く理解できるか、自分を試したかった
・藤井風さんの音楽なら1年間、心折れずに向き合えそう
・デビュー時期ともタイミングが重なり、この1年間精力的に活動されるだろうと思った
などの目的やイメージがあった。
風さん(と呼ばせていただくことにする)のことは業界でも数年前から、プロが驚くほどの逸材だと話題になっていたが、好奇の目で見たくなかったので、知人づてに名前を聞く程度だった。
「風」という印象的な名前が記憶にとどまる。
初めてオリジナル曲を聴いたのは、2019年11月だった。
2020年1月「何なんw」でデビュー
プロが驚くとは?前評判に関係なく、私は自分のものさしで良い音楽を聴いていくんじゃ。騙されない、負けないぞ。再生はするけども、ポチッ。
はいっ負けました。大好きです私をぶんぶんに振り回してください。
岡山弁のニュアンスを壊さずに、裏拍をこんなにグルーヴィーに表現できるのか。「あんた」という響きが良い。英語では十把一絡げに「You」とされるのが惜しいくらいだ。
歌詞は、ハイヤーセルフが自分に語りかけている内容だという。しかもこのハイヤーセルフさんは健気だ。
ハイヤーセルフとは高次の意識、人格を超えた自分の魂みたいなものだ。私も心理学を勉強した時に少しかじった程度なので偉そうに語れないが。
この高次なテーマが、ソウルフルでJazzyなスイングと絡まるのにタイトルには草が生え、歯に挟まったあおさの話で始まるミクスチャー。発明の話なのか。
曲ごとに解説やMVのBehind The Scenesも制作され、コンテンツとしてのクオリティが高い。
英語も堪能で、内なるエネルギーをアウトプットすることに長けているのではないだろうか。
その点では、風さんには英語の方が、思想を伝えるのに言語としてフィットするかもしれないとも思った。いずれにせよ世界に羽ばたくべき人だ。
SNSも含め、総じて「発信」がとても上手だ。まったく人様の評価をしている場合ではないけど。
EP「もうええわ」リリース
2月には、先行配信されていた「もうええわ」のEPをリリース。レトロなMIXがとても良い。
MVでは、柴犬のいぶきちゃん登場で必ず高めの声が出る。私はもう、どの辺りにカーソルを合わせればいぶきちゃんが出てくるか熟知している。いぶき命。
岡山弁のニュアンスを、英語ならどうローカライズするだろうと考える歌詞である。世界を見据えつつも、日本語と故郷を大切にしているのは藤井風さんの大きな魅力なので、日本語以外でも伝わってほしいと願う。
全4曲中、2〜4曲目は弾き語りカバーで、iTunesなどのダウンロードサイト限定。つまりリード曲以外、Spotifyなどのストリーミングでは扱っていない。
上手い売り出し方だなと思うが、嫌な気はしない。そんなことより、O’Jaysまでカバーする選曲に好感が持てる。
そのクオリティもすごい。ただ人の曲をなぞるだけでもなければ、持ち歌かのようにいいとこ取りして掻っさらうでもない。とてもちょうどいい。
ところで「もうええわ」は、2000年代の名曲COMA-CHIさんの「ミチバタ」など、日本のHIPHOPに影響を受けたそうだ。
「ミチバタ」のオマージュとなっているのがBlack Sheepの「Without A Doubt」、そしてその曲もThe Isley Brothersのメロウな名曲「The highway of my life」をサンプリングしている。
楽曲を紐解くと思わぬ名曲にたどり着く。これこそが、音楽が我々に与えてくれる素晴らしい体験ではないだろうか。アーティストの深い知識はその体験を支えてくれる。
風さんがご実家でブラックミュージックから演歌まで、多様な音楽に触れて育ったことも教養となり、世の中に還元されていると思うと感慨深い。
教養とは、自分自身が生き抜くために身に付けるものだと思ってきた。
ライターで言えば、読書で知識を得たり語彙量を増やすことも、世の中に還元されるなら喜んで学びたい。私だって読んで下さる方を笑顔にしたいのだ!自分の知識がそれを支える。風さんありがとう頑張るよ。
それはそうと、見る度に違う表情をする風さん。目を見張るパフォーマンスをしたと思うと、岡山弁で訥々と話し出す。
YouTubeのドキュメンタリー見よるけど
わしのしゃべり方は、アレやな2倍速にして丁度ええやつじゃ pic.twitter.com/7UwFwc6mTs
— Fujii Kaze (@FujiiKaze) August 12, 2020
ピアノを弾く指はあんなに速く動くのに、とてもゆっくりとお話される。
「藤井風って2, 3人いるんだぜ」と言われても「もっといるんだろ」と詰め寄れる自信があるほどギャップの溝が深い。
なんて愛にあふれた方なのだ。当初誤解していたことを風さんに謝りたい。内面を知ると曲の聴こえ方も変わるので、やはり芸術は作り手の体温が理解を深めるものだと実感する。
このYouTube主催の「Artist on the Rise」は話題の新しいアーティストがピックアップされるが、国内第1回目として藤井風さんが選出された。YouTubeがきっかけでデビューを果たした彼にはぴったりのプロジェクトである。
風さんは長年、ご自身のYouTubeチャンネルにたくさんのカバー動画をアップされてきた。
カバー動画がすごすぎる
どうやら、これらのカバー動画は以前にも拝見していたようだ。ジャンルを問わず、音楽を愛してきた歴史を感じる。
ウィスパー系も上手い、VERBALさんのラップパートもこなす。やればドラムも上手そう。
個人的には容赦ない強めの打鍵がクセになる。でも細部にまで神経が行き届いていて、グルーヴ重視といった感じ。風さんのピアノは、譜面にはない情熱を伝えてくれる気がする。
何を考えているのか読めない表情、どこを見ているのか分からない視線。自分の軸を持ちながらも、オリジナルへの愛とリスペクトを感じる。
沼にハマった皆さんは睡眠を削ってご覧になっているらしい。そうだよね、可処分時間足りないよね。
YouTubeのコメント欄には「一切の家事やらなくていいから横で弾き語りしててほしい」「抱かれたいけど抱かないで車で帰ってほしい」「身分隠してるどっかの国の王子みたい」など意味不明だが分かりみの深いコメントが多数。皿洗いくらいはやってほしい。
お兄さんとのsolakazeチャンネルでは歌謡曲なども多く、そちらも捨てがたい。テレサ・テンが最高だった。
アルバム『HELP EVER HURT NEVER』
5月にはアルバム『HELP EVER HURT NEVER』のCD、9月にはレコードがリリースされた。私はレコードを購入したのだが、これは「名盤」であると断言しよう。
アナログはデジタルと聴こえ方が違い、好きな曲も異なる。
「死ぬのがいいわ」「罪の香り」は味が出て表情が変わるし、中でもアナログでは「風よ」の存在感が大好きだ。
哀愁漂い、自分が今どの時代にいるのか分からなくなるが、どの時代だろうと関係ない。ストリーミングでは静かで暗いイメージかもしれないけれど、アナログだととてもしっくりくる。
トップ画像にあるポータブルプレイヤーも手軽で良いのだが、スピーカーで本格的に聴くことにハマっている。
アルバムリードの「帰ろう」は、たった5分で聴いた人の数だけ死生観が更新されるような曲だと思った。
真っ直ぐなメロディに、壮大なストリングスとドラムで奥行きが生まれ、そこに纏われた歌詞が深みを与えている。
「何なんw」のグルーヴに対し、こちらは物語の語り手のようなヴォーカルだ。
どの曲もそうだけれど、深く吸い込むのか、エッジボイスで文脈が繋がるように呼吸するのかといった選択が絶妙で鋭い。
日本語の文章を読み上げる時、どのブロックで区切っても意味が伝わるという特徴がある。だからこそ、どこに読点(、)を打つかでニュアンスが変わる。
風さんの曲では、ブレスが自然とその役割を果たしているように思う。
憎み合いの果てに何が生まれるの
わたし、わたしが先に 忘れよう
「わたし」まで歌い切ることで意味が強調されたり、フレーズにインパクトやメリハリが生まれる。
それにしても「わたしが先に忘れよう」とはとても良い言葉だ。自分もそうしようと本気で思う。忘れるというのは、実はすごい技術なのかもしれない。
そして、このアルバムを名盤たらしめているのは、風さんの並々ならぬ「覚悟」だと思った。
1stアルバムでこの世界観を見出すには、技術的にも精神的にも、あらゆる面でここに到達する準備ができていなければ、確立できないのではないだろうか。
あまりそういう素振りを見せる方ではないが、ずっと準備してきたのだろう。
デビューして、やりながら磨けばいいという生半可ではない覚悟。周りの方々もそれを受け止めているのではないかなと。
この1年の中で、風さんの覚悟に私はいたく感動した。その最たる形がこのアルバムである。
初の武道館ライブ
10月29日、日本武道館での有観客ライブは配信で拝見した。
デビュー1年足らずでの武道館公演がコロナ禍で開催され、それを生配信される状況。大変だったと思うけれど、とても配慮が行き届いていた。
公演に踏み切ったことで、業界にどれだけ勇気を与えられたかは計り知れない。
コロナ対策で換気をするための2部構成だったが、前半はカバー中心でシンプルに、後半はオリジナル曲で華やかなステージで、気持ちを切り替えることもできた。
風さんのアーティスト活動の原点でもあるカバー曲を含むセットリストも良かった。
家族連れなど、休憩タイムがあると助かるという方もいるのではないだろうか。サッカーの観戦に行っても、ハーフタイムで飲んで食べてしゃべるのが楽しかったりするよね。
6月に開催されるはずだったライブが中止になった時、風さんはYouTubeで弾き語りライブを配信してくれた。
ご自身だって肩を落としていたはずなのに「大変なことも多いじゃろうけど、落ち着いていたら絶対わしら大丈夫やけん。いつも冷静に、優しく」と励ましてくれた。
そんな風さんが武道館のステージに立っている。「落ち着いたら絶対大丈夫やけん」と画面越しに何度もエールを送った。今でも日常的にこの言葉が脳裏に浮かんだりする。
この日は新曲「へでもねーよ」と「青春病」を初披露。翌日には同時配信リリースされた。
「へでもねーよ」「青春病」同時リリース
名盤の後の挑発的なタイトル。生意気だとも言われかねないのに、安全圏にとどまらないスタイルで突き進んでいる。
しかし「へでもねーよ」は己のネガティブな感情に対する、自照性を極めたような曲だと思うので、強烈なインパクトを与えれば与えるほど、そのメンタリティのかっこよさが際立つ。
とりあえず曲展開は変態だ。藤井風チーム、どんな連携体制なのだ。底知れぬ実力に身震いがする。このイントロからアウトロにたどり着くなんて、誰が想像できるか。
2Aのリフなんて近未来のわらべ歌かと思った。Bメロは、1番ではストリングスで天国にいざなわれ、2番はこの世で唯一の救いのような美しいピアノが前面に出ている。この世なのかあの世なのか。
武道館の翌日にこんなの出されたら「好きになる」以外押すボタンがない。
そしてアウトロの「おおお〜ええぃ〜」とサビが混ざり合って最強のイヤフォン推奨曲となった瞬間にこの曲は召される。
「青春病」は立ち上がりこそ軽快な印象も受けるが、徐々に重さを増す。つまり親善試合だと思っていたら、ハーフタイム(間奏)に実はトーナメント戦だったと告げられたような曲。青春は複雑なのだ。
2番はサビがなく、印象的なブリッジから大サビへと繋がる。これは大胆なサイドチェンジからの華麗なパス回し、大サビの2列目からの飛び出しによって劇的ゴールを生んだことを意味する。優勝です。
このブリッジはシュート意識の高いボランチだ。特に、後半75分で投入された“切れど切れど纏わりつく”からの畳み掛けは、スーパーサブとして見事に展開を変えた。
MOMは決勝点を決めた大サビであったが、このチームを献身的に支えたのは言うまでもなく、後半に豊富な運動量を発揮したベテラン、センターバックのベースである。
この曲はCulture Cruiseのトップソング、いわば年間ベストイレブンにも選出された。
【1年分のプレイリストが完成!】Culture Cruiseが選ぶ2020年トップソングを発表します
ホールツアー『HELP EVER HALL TOUR』
そして12月からはホールツアーを開催。
12月25日のチケットが奇跡的に当選したが、行けない方も多いと聞くので、大切に拝見したい。この時期での開催なので、何事もなくツアーが成功することを何よりも願う。
ライブを見届けてから公開するか迷ったけれど、自分にとってはこの日が、もう次のスタートかもしれない。それはその瞬間を迎えてみなければ分からないので、記事は一旦終わらせようと思う(長いし)。
この記事が手を離れたら、どうしようかなぁ。寂しさを感じるほど、1年間、泣いたり笑ったりしながら綴ってきた。
上手く書けずに、繰り返し同じメロディーをなぞったけれど、最後まで1曲たりとも飽きることなく、どんどん大切になっていった。
自分の弱い心は何度もくじけそうになったのに、風さんの音楽はずっと離れずにいてくれた。
また風さんの記事、書いても良いですか? そうすれば寂しくなることもなく、心が晴れていくような気がします。
あとがき
ーー記事を書き始めた当初は、風さんの人となりを存じ上げていませんでした。イメージした人物像は、クールで澄ました感じ、自分中心に世界を回すような芸術家タイプ(ごめんなさい)。
どんな方だろうと、テーマは音楽なので、1年で1記事を書き上げるコンセプトは変わらなかったと思います。
けれど記事を書くにつれ、楽曲だけにとどまらず、風さんの人柄としての魅力を感じずにはいられませんでした。
ここで伝えるべきは風さんのそういう姿なのではないか、という気持ちに変わっていったほどです。
稀にみる天才とか、誰々の再来だとか、しばらく言われ続けるのだろうけれど、風さんは風さんだし、大好きな歌を歌っていられることが大切で、ファンは誰もがそれを願っている。
デビューしてわずか1年で、ここまで礎を築くのもすごいことです。
だからこそ、彗星のごとく現れた天才と捉えられるのかもしれませんが、きっと礎のすべては鍛錬の積み重ねです。
風さんから私が感じた「覚悟」は、その片鱗にすぎないのだと思います。
それに比べて、同じ1年でも私の記事を書くスピードはちっとも速まりませんでした。むしろ遅くなったのでは? きっとまた怒られます。
けれど、だからこそこの記事が存在し、1年間心の拠り所にもなってくれました。
藤井風さんの音楽とはどういうものか、1年後の自分に教えてもらえることを楽しみにしています。
まえがきでこう綴った自分に返事を書いて、この記事を終わりにしたいと思います。
藤井風さんの音楽に触れた2020年の私は、音楽の強さを知ることができた。
「5分前より、心が豊かになる音楽」それが、藤井風さんの音楽なんだよ。
2020年12月 長谷川 チエ
▼後日書いたライブレポートはこちら
▼『旅路』レビュー