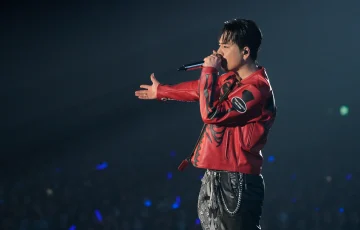2019年6月、Aviciiの遺作となるアルバム『TIM』がリリースされました。今回はこのアルバムとともに、Aviciiの代表作を振り返ります。
Aviciiについて
Avicii(アヴィーチー・本名:Tim Bergling)は1989年、スウェーデン生まれ。母は役者で、自然と音楽に触れる環境の中、音楽家になる夢を抱きながら裕福な家庭で育ちました。
高校卒業後の2006年頃から、自ら楽曲制作し、リミックスを手がけるようになります。その作品の数々を自身のブログにアップし続けるところから、彼の本格的な音楽人生はスタートしました。
イギリスのDJ主催イベントで優勝するなどして、2008年にはAt Night Managementと契約。
その後はDJ、アーティスト、音楽プロデューサーとして世界的に脚光を浴び、ヒット作を次々に連発。2016年にはDJからの引退を発表しますが、人気は衰えず、音楽活動は継続していました。
しかし2018年4月、滞在先のオマーンにて28歳で突然の死を迎えます。家族の手紙によると、自殺であった旨が示唆されていたそうです。
日本への来日チャンスは何度もあり、実際にブッキングもされていたのですが、直前でのキャンセルが続きました。結局、2016年に大阪と千葉で行われた「AVICII JAPAN TOUR 2016」が最初で最後の来日公演となりました。
今回この記事を書いたのは、彼の死について語りたいわけでも、感傷に浸りたいわけでもなく、彼の遺した作品の素晴らしさを自分の記事にまとめておきたいと思ったからです。
他ジャンルを実験的にミックスさせ、じっくり聴けるEDMを数多く作り出してくれたAvicii。EDMを世界的なメインストリームに押し上げたといっても過言ではありません。
Aviciiが発表したほんの一部の楽曲にすぎませんが、彼の代表作を振り返ります。
Seek Bromance(2010年)
彼のディスコグラフィはこの頃から始まります。Aviciiとして活動する前のTim Berg名義で、2010年にリリースした楽曲。
ザ・EDMなサウンドが世界的に流行していた頃ですが、その後のライブやイベントでもこの曲はよくプレイしていました。
一見、男女3人の友情がテーマの青春っぽいMVですが、そもそも「Bromance」とは、「Brother」と「Romance」が掛け合わされた表現で、男性同士の親密な友情を指す言葉です。それを踏まえてMVを観るとまた複雑に感じます。
Fade Into Darkness(2011年)
ヴォーカルを引き立たせる要素は、Aviciiの楽曲に共通した素晴らしさだとも思いますし、その片鱗を感じ取ることができます。
爽やかな曲調ですが、「We won’t fade into darkness」というフレーズが何度も何度も叫ばれます。光と闇の対比によって、深い世界が表現されています。
Levels(2011年)
Aviciiはこの曲で一気にスターダムへのし上がることに。当時、世界中で流行しました。この曲でここまで表現できてしまうのかと、MVに衝撃を受けたことを覚えています。
EDMはクリックさえできれば作れるという批判の声も高まる中、エレクトロの中に人間性を見出すという、EDMの奥深さを痛感しました。
I Could Be The One- Avicii vs Nicky Romero(2013年)
Aviciiと同じく、DJ・音楽プロデューサーとして世界的な人気を誇る、同い年で親交の深かったNicky Romeroとのコラボ作。ライブでも鉄板曲として大人気でした。
自分をストレスから解放しようという趣旨の内容で、ユニークですが衝撃的なラストを迎えるMVも当時話題になりました。
この曲にはアコースティックバージョンもあります。
ヴォーカルはNoonie Bao (ヌーニー・バオ)というシンガーなのですが、最新アルバム『TIM』でもコラボしています。アコースティックにすると雰囲気が変わりますね。
Wake Me Up(2013年)
Aviciiを語る上でこれは外せないほどの、Avicii最大のヒット曲。世界69ヶ国で1位を獲得しました。
Aloe Blaccをフィーチャーし、EDMでありながらフォークサウンドを取り入れたメロディックな楽曲。EDMになじみのないリスナーにも支持されました。
Aloe Blaccは元々ソウルシンガーとして活動していましたが、この曲によって世界的な人気を獲得し、過去の作品までもが脚光を浴びることに。
The Days(2014年)
元Take Thatのメンバー、Robbie Williamsをヴォーカルに迎えた作品。E.P.としてともにリリースされた「The Nights」と聴き比べるのも興味深いです。
Aviciiの曲の中ではヒット作とは言えないかもしれないのですが、私はこの曲とこのMVが非常に好きです。シンプルですがカラフルでクリエイティブで、自由を感じます。
Lonely Together ft. Rita Ora(2017年)
Rita Oraをフィーチャーしたこの曲も大ヒットしました。Rita Oraの存在感を見せつけられます。
叶わぬ恋に、ひたすら「Let’ s be lonely together」と嘆き、「あなたと一緒なら孤独も少しは消える」という曲です。でも二人きりの孤独は、一人きりよりも孤独なのではないか…と最近考えたりします(暗)。
2019年、最後のアルバム『TIM』をリリース
2019年6月、Aviciiの最後のアルバムがリリースされました。楽曲自体は生前にある程度制作されていた状態だったもので、家族の意向などにより、リリースすることが決定。
未完成部分は製作陣にバトンが受け継がれましたが、Aviciiのメモ書きなどを元にパズルをつなぎ合わせていく作業は難航を極めたそうです。
Aviciiが伝えたかった原曲の世界観を壊すことなく完成させるのは、至難の業であったことは想像に難くありません。
しかし仕上がりを聴いてみると、Aviciiがすぐそこにいるかのような錯覚に陥るほど、完成度の高いアルバムだと思いました。もちろん彼がどの部分まで制作していたかは分かりませんが、とてもAviciiらしさを感じる美しいアレンジではないかと。
ちなみに『TIM』とはAviciiの本名で、アルバム名も家族が命名したそうです。
- Peace Of Mind feat. Vargas & Lagola
- Heaven
- SOS feat. Aloe Blacc
- Tough Love feat. Agnes, Vargas & Lagola
- Bad Reputation feat. Joe Janiak
- Ain’t A Thing feat. Bonn
- Hold The Line feat. A R I Z O N A
- Freak feat. Bonn
- Excuse Me Mr Sir feat. Vargas & Lagola
- Heart Upon My Sleeve feat. Imagine Dragons
- Never Leave Me feat. Joe Janiak
- Fades Away feat. Noonie Bao
SOS ft. Aloe Blacc
アルバムに先駆けて配信されていたリードシングル。「Wake Me Up」で大ヒットを飛ばしたAloe Blaccとも再びタッグを組んでいたのですね。Aloe Blaccのディープな歌唱力と、それに負けないほどのトラックの素晴らしさ。
Heaven
生前からコラボすることの多かったColdplayのヴォーカル、Chris Martinとコラボした曲。2014年にはレコーディングを済ませていたそうです。
深みのあるChrisのヴォーカルとも非常に良く合っていて、引き込まれる独特の世界観と映像美に見入ってしまいます。
アルバム『TIM』では他にも、Vargas & Lagola、Imagine Dragons、Joe Janiak、Noonie Baoらともコラボしています。
坂本九「上を向いて歩こう」をサンプリングした「Freak feat.Bonn」なども話題に。BonnはMartin Garrixや5 Seconds of Summerのコラボレーターとしても知られているアーティストです。
このアルバムによって、Tim Berglingとしての姿を見せてくれたような気がしました。
ヒット作を次々と世に送り出してきたAviciiですが、個人的に好きなのはどれも、そこまでヒットしなかったなぁという作品が多い気がします(それでも十分売れているのですが)。
Aviciiにとっては楽曲がヒットすることよりも、伝えたいメッセージを伝えることの方が重要だったのではないかとも感じています。
世界中に数えきれないほどのDJやトラックメイカーがいる中で、Aviciiの作品がヒットし続けたのは、人の心に触れる音楽を作ってきたからだと思うのです。
AviciiはEDMがロマンチックで奥深い音楽であることを世界中に教えてくれたし、ダンスミュージックを聴かない人たちをもリスナーとして迎え入れた。
数々の賞を受賞してきたけれど、私が思う彼の音楽の素晴らしさは、たくさんの人たちを一つの音楽で繋げてくれたという点です。
リリースすればすぐに古くなっていくエレクトロな世界の中心に生きていた彼は、何を感じ、何を提示してくれていたのか。
自らの音楽性を壊すことなく、表現力の限界までトライしていたように思うし、その限界を突破していたと思います。
時代は新しいものを求めているようだけれど、彼の作品の素晴らしさはこの先もずっと変わらず、色褪せないはずです。
R.I.P Avicii, 1989 – Forever.
▼ザ・ウィークエンド『Dawn FM』レビュー