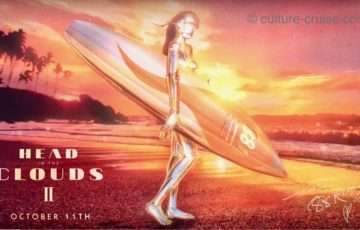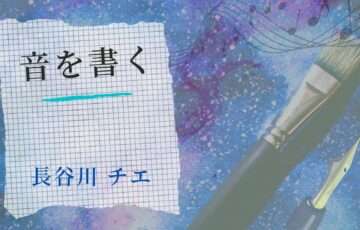2023年5月24日にコラボシングル「How’s The Weather?」をリリースしたaimiさん、EMI MARIAさんにインタビュー。第二弾となる今作の制作について伺いました。
aimi × EMI MARIA × Culture Cruise
ーーおふたりとは楽曲のプレスリリースを掲載させていただいていましたが、『STAY READY』(2022年12月に行われたaimiさん主催のイベント。EMI MARIAさんもゲスト出演)でやっとご挨拶させていただけました。
aimi:あのイベントからここに繋がるとは。嬉しかったです。
EMI MARIA(以下、EMI):ありがとうございます! あの時はまだ今回のリリースのことも決まってなかったよね。
ーー作ろうとしてるんだけど、くらいでしたもんね。おふたりには絶対にインタビューしたいと決めていたのですが、aimiさんから曲ができたとご連絡いただいたので、今しかない! と思って。
aimi:『STAY READY』の後にEMIさんが着手し始めて、先に「Priority」のデモを送ってきてくれて「これはヤバい!絶対進めよう」と思いました。「How’s The Weather?」のビートは私もEMIさんも気に入ってて、こっちも絶対なにか作ろうねって話してたんです。コンセプトやサビの歌詞は、電話で一緒に作りましたね。
ーービデオ通話でもなく、電話なんですね。
aimi:視覚的情報がない方がやりやすいのかもしれないですね。EMIさんはお子さんもいるからゴールデンタイムが短くて、会う方が移動の時間がもったいないし、会うと盛り上がっちゃうし(笑)。電話が一番作業に集中できるかな。
EMI:ボイスメモ送りあって「こういう歌い方で」とか。お互いにラララで歌って、(プロデューサーの)Modesty Beatsがメロを組み合わせたものに、お互いに歌詞を書いていきました。
aimi:それを私たちは「メロコンペ」と呼んでいて、メロディのコンペティションという意味です。お互いにとっておきのメロをまるっと1曲書いて、一番おいしい部分をModestyが選べるという。
ーーすごいことしてますよね。
aimi:「How’s The Weather?」のブリッジの「吸って 吐いて」のところは元々サビのメロだった気がするんだよな。EMIさんの。
EMI:そうだった。
aimi:サビで使ってたコーラスがアウトロに来てたりとか。パズルです。R&Bだからできることかもしれないですね。ループミュージックだから。J-POPはコード進行に制約があると、決まったセクションで使うしかないので、あちこち移動できないじゃないですか。
ーーそれもR&Bの魅力ですね。「Priority」は、インスタライブでも「交換日記のような制作だった」とおっしゃっていましたが、どのように進行しましたか?
EMI:実際に会ったのは2回くらいで、ほとんどLINEでデータのやり取りをしていましたね。
aimi:EMIさんに「このままメロディを作ってください」とお願いして、私が歌詞書いて送って、歌ってもらって。でもしっくり来ないから違うメロ送ってもらって…永遠にそのやり取りで。
EMI:1, 2月でそれをやっていましたね。
共鳴を感じたリスナーからの反応
ーー「How’s The Weather?」について、リスナーからの反応はいかがでしたか?
aimi:みんなこのR&B度数を、思った以上に受け入れてくれるんだと思いましたね。2回目のコラボということもあって、私たちのやりたいことを思いっきりやっているんですね。メロウすぎるかなとか、全英詞の曲もあって取っ付きづらいかなとか、我々なりに思ったんですけど。
ーーやりたいことを貫いたのもよかったのかなと思いますね。
aimi:やりたいことをやったら、意外とみんなと共鳴したなという感じですね。「セルフケア」というテーマもあって、親しみやすく感じてもらえたポイントだったのかなと思いました。「自分はもっと息を吸って吐けたんだって気付いた」とか。自分と照らし合わせてコメントしてくれるのも大きな変化で。
EMI:私も、このR&Bを受け入れてくれる人がこんなにいるんだということにびっくりしました。
ーーそれは裏を返せば、受け入れてくれなくてもいいという覚悟で制作したということなのでしょうか?
aimi:たしかに。この曲大好きだったので、出せただけで満たされたというか。そしたらもれなくみんなも満たされていったのがすごい面白かった。サウンドと違うところでもコネクトできて。
ーーR&Bのコネクトの仕方としては珍しいかもしれないですよね。
aimi:誰にでも刺さるヒットを飛ばそうとか、チャートインを目指すとか、そんなことをやってたわけじゃなくて、これを分かってくれる人に伝わればいいという思いで。第二弾を出すにあたって一番変わったのが私たち2人の信頼関係で、R&Bを届けるんじゃなくて、心のメッセージを届けるために曲を出すというマインドにシフトしてたことが、みんなに伝わったのかなと。
EMI:みんなもそう感じていたんだなという「共感の部分」にも驚きましたね。
aimi:サウンドでいうとサマー・ウォーカーとかジャズミン・サリヴァンあたりがメインでやっているようなビート感、そういうメロウでチルなベースがブンブン鳴ってて、でもミニマルトラックな感じって、一昔前だったらアルバム曲にされちゃうようなテイストなのかもしれないですけど。これが受け入れられる土俵があるという、音楽に対してリスナーが寛容的になったのかな。
ーーことR&Bに関しては敷居が高かったイメージもありますが、サブスクで耳が馴染んだのもあって、一気にハードルも下がって、リスナーが聴くR&Bの幅も広がっている気がします。
aimi:プレイリストの中でも、いろんなサウンドに出会うことが多いじゃないですか。次はこれ、次は全然違う曲、って流れで聴くから、受け入れてもらえるのはあるかもしれないですね。
ーージャンルで括らずに聴くスタイルになっているようにも思いますね。個人的に今作からは、メロディとしてはR&Bのトラディショナルなマナーも保ちつつ、2023年の現行のビート感も感じました。そういったバランスなどを意識することはありますか?
EMI:まったく意識してないかも。
aimi:(しばらく考えて)してないかもね。ビートにインスパイアされて、自然とバランスが取れている感じがしますね。
ーーお互いにそうなのかもしれないですね。プロデューサー側もメロディに引っ張られたり。
aimi:そうかもしれないですね。例えばHIPHOPだったらビート先行で作ってるだろうなって誰しも思ってるじゃないですか。でも歌ものになった途端に、ピアノ弾いて作ってるんじゃないかと思う人もいると思うんですが。
ーー弾き語りと同時に生まれてくるメロディみたいな(笑)。
aimi:そうそう。アーティストがデモ音源を作るやり方もたしかにあるんですけど、私たちの場合は海外のスタイルに近くて、ビートを先にもらってその世界観にメロディを当て込んでいく作業で。ビートの方向性はプロデューサーが打ち出してるものがあるから、いい意味でビートが新しいと、我々は大船に乗った気持ちで、懐かしいメロディにしてハイブリッドになるみたいな。
EMI:私にとってはこのコラボは異質というか、説明しなくても分かってくれるし、R&B詳しい人同士がやるとこうなるんだって思いました。「このMIXだったらこうだよね」とか認識が近くて。
aimi:共通言語が多いから「この音は大きくしたいね」「ここは歌詞を強調したいね」とかの小さなアプローチの仕方が近いところにあって、作品がまとまりやすかった。戦った覚えがなくて。
ーーそもそもModesty Beatsさんと制作することになったきっかけは何ですか?
aimi:Modesty Beatsは、実は某プロデューサーの別名義なんですよ。やりたいことがいっぱいあるのに、今までのイメージに引っ張られちゃうというか、バイアスをなくしたいということで名義を変えているみたいで。
ーーそうだったんですね! 調べても全然出てこないから「新人さんなのかな、それにしてはこんなクオリティで出せるわけないよな」とか考えていました。
EMI:そう思いますよね(笑)!
お互いの印象について

ーーおふたりはInstagramのDMから繋がったそうですが、aimiさんから見てEMIさんはどんなアーティストですか?
EMI:なんで私とコラボしたいと思ったのか謎なんだけど(笑)。
aimi:EMIさんの過去の作品で、特にインディペンデントになった2017年頃の作品をYouTubeで観て「あなたは世界に行く人です」って英語のコメントがいっぱいあってそれに納得して、でもオリジナルを出していなかった数年間があって。そしたらカバーを出し始めたから「この人動き出すぞ!」って匂いがして(笑)。動きだしたら絶対に一緒にやりたいって心に決めてたんです。そしたらInstagramでフォローバックしてくれたのでDMして「お茶行きませんか?」って。
ーーいきなりお茶なのがいいですね。
aimi:日本でコラボしたいアーティストって聞かれたらEMI MARIAってずっと言ってたんです。実際にコラボしてみて、音楽的に合うのはもちろん、人間的にこんなにも合うのかっていうのが衝撃で、出会うべくして出会ったという感じです。アーティストとしてのリスペクトは今も変わらないけど、一緒に曲を作る運命だったんだと思ってます。運命の相手です(笑)。
EMI:aimiちゃんはちょうどコロナの頃(2020年)に出てきて、日本語を交えつつ、ネイティブにも伝わる英語で歌える人がやっと出てきたなと思って、正直自分もthread(恐れる)じゃないけど、頑張らないとと思わされたし、嬉しいことでもあって。私はしばらく休んだ後にカバーとかを出して、その時動き出そうとはまったく思ってなかったんですけど。
aimi:そうなんだ! 私が勝手に決めつけてた(笑)。
EMI:プライベートでアーティストとご飯行くとかも全然なかったし、他の人とはあまり行きたいと思わなかったんですけど、aimiちゃんとはまじで行きたいと思って。知らない人と会うのとか緊張するんですけど、自分をオープンにできそうと勝手に思って。そしたら一緒に曲作りたいって言ってくれて。
aimi:「私も作りたい」って二つ返事で答えてくれたんです。
EMI:そこからトントン拍子に。2022年の3月頃に会って、夏頃から「Day N Night」を制作して。aimiちゃんはこの企画のために何でもしてくれて、みんなのために動いてくれて、こんなアーティストがいるんだって思いましたね。アーティストとしても素晴らしいのに、プロジェクトのために裏方でも綿密にやっていて。将来めちゃくちゃすごいやつになるなって(笑)。人のいいところが良く見えてて、一緒にいて勉強になるし楽しいし、かつ音楽の部分でも共鳴しあえるのが感動です。aimiちゃんと出会って、自分も心がオープンになってきた気がして。不思議な力が働いてるというか、何かに呼ばれて制作していると思ってて、これが終わってしまうのが寂しくて。
aimi:だから今日も「次会う予定ないね、作ろう」ってどうにか続けようとして(笑)。お互いに“Priority”があるから、何とか優先順位を上げるmatterを作っちゃおうという。
ーーEMIさんは動き出すつもりではなかったのに、aimiさんから一緒に曲作りたいと言われて「私も」と言った時、どんな心境だったのですか?
EMI:曲は一緒に作れると思っていなかったですね。私はコラボするタイプでもなかったですし、コラボは作ってる過程でぶつかるんじゃないかって不安もあって。自分がこだわるところもあるし、相手とすり合わせるのは難しいと思っていたので。今回こんなに上手くいったのはまじで奇跡だなと思います。
aimi:勇気を振り絞ってくれたんですね。
EMI:できそうだなって思ったんですよね。
ーー今後の活動については、何かお聞かせいただけることはありますか?
aimi:『STAY READY』を夏頃にもう一度できたらいいなと思っているんです。前回はほぼ私1人で企画運営したものだったので、少しパワーアップした形でアクトを増やせればいいなと思って、そのために動いている状況です。
ーー12月のイベントは私も本当に感動して、オーガナイザーのaimiさんの思いがフロアに伝染するというか、こんなことあるんだって泣きそうになりました。
aimi:嬉しい…なんかありましたよね。今まで本音でぶつかり合うことってなかったんですよ。実績もないし自信もないし、ライブパフォーマンスにおいてもまだまだ勉強中だったんですけど、あの時にそれが満ちて、R&Bに対しての想いが大爆発して。それに対してみんなが反応してくれて、後々言葉にするのが惜しいくらいの気持ちでした。
ーーおふたりのステージパフォーマンスは本当に最高なので、ぜひたくさんの方に届いて欲しいなと思います。
編集後記
aimiさん、EMI MARIAさん、念願のおふたりへの同時インタビューと、こんなに素敵な作品について取材できたことを嬉しく思います。
インタビューを受けるというスタンスではなく、一緒に話そうと心を開いてくれるのがaimiさん。日本語も英語も、豊富な語彙を駆使して行き来する話しぶり、論理的でエッジの効いた言葉選びは、話したままを文章にできるくらいにスマートなのですが、常に周りを気遣う優しさも忘れない。またお話したいと思わせてくれる素敵な方でした。
EMI MARIAさんの甘くて芯のあるヴォーカルが大好きでしたが、お会いして優しさに触れると、そのきめ細やかな心がEMIさんの表現力となり、歌声を生み出しているのだと分かりました。長いキャリアの中でも変わらずにいてくれたことで、2023年に「How’s The Weather?」へ辿り着き、リスナーとして最高のR&Bを受け取れたことが本当に嬉しいです。
おふたりの活動を今後も取材していきたいと思います。
インタビュー・文 / 長谷川 チエ
▼Instagramでは取材日記やライブレポートも更新中